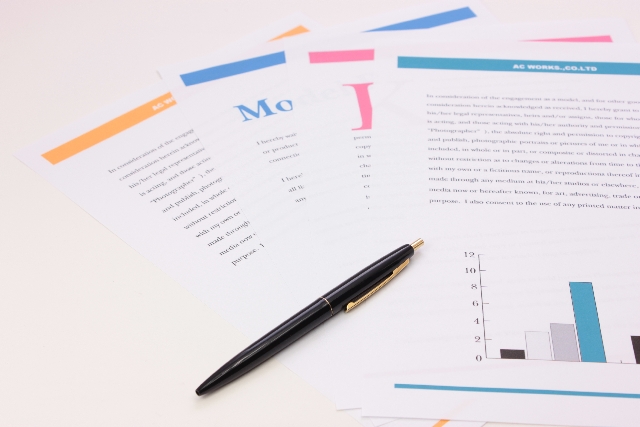


税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
補足を受けて:
住民税の天引きを今の会社が面倒くさがったんでしょうね。
次の会社には6月頃市町村から次の納付書が届くでしょうから、
対応が可能か聞いてみてください。
それからすでに次の会社が決まってますから、
再就職手当は不可能です。
入社日ではなく、いつ内定をもらったかが重要です。
そんなことに力を注がないでください。
1.毎月のお給料と直結して変動するのは雇用保険料と所得税です。
健康保険料と厚生年金保険料は
毎年4月から6月の収入をもとにその年の9月から翌年の8月までが決まります。
↑これが基本ですが、他には入社時にこの人はこれくらい稼ぐと契約書などから算出したりします。
住民税は1月から12月までのお給料をもとに
翌年の6月からさらに翌々年の5月までの金額が決まります。
したがって、大きく考えれば
健康保険料・厚生年金保険料・住民税も
収入によって異なります。
2.平成23年1月から12月には収入はありましたか?
あったとして年間90万を越えましたか?
住民税は天引きとは限りません。
市町村から直接納付書が届く場合があります。
特に平成23年12月に勤務していた会社を
平成24年6月までに退社していた場合は納付書が来ます。
この辺りは少し補足してください。
3.3月31日に退職した時点では
次の会社が決まっていますので、
雇用保険などからは何もありません。
でも、払い損ではなく、
次退職するときに勤務年数に追加されます。
例えば次の会社と残念ながらご縁が無く3ヶ月くらいで退職した場合
次の会社だけでは失業保険をもらう権利は無いですが、
今の会社で7ヶ月以上加入していれば
足し算して1年以上になり失業保険をもらえます。
5年以上や10年以上などで給付日数が変わりますが、
その辺りにも足されますので
払い損ではないので、ご安心を。
住民税の天引きを今の会社が面倒くさがったんでしょうね。
次の会社には6月頃市町村から次の納付書が届くでしょうから、
対応が可能か聞いてみてください。
それからすでに次の会社が決まってますから、
再就職手当は不可能です。
入社日ではなく、いつ内定をもらったかが重要です。
そんなことに力を注がないでください。
1.毎月のお給料と直結して変動するのは雇用保険料と所得税です。
健康保険料と厚生年金保険料は
毎年4月から6月の収入をもとにその年の9月から翌年の8月までが決まります。
↑これが基本ですが、他には入社時にこの人はこれくらい稼ぐと契約書などから算出したりします。
住民税は1月から12月までのお給料をもとに
翌年の6月からさらに翌々年の5月までの金額が決まります。
したがって、大きく考えれば
健康保険料・厚生年金保険料・住民税も
収入によって異なります。
2.平成23年1月から12月には収入はありましたか?
あったとして年間90万を越えましたか?
住民税は天引きとは限りません。
市町村から直接納付書が届く場合があります。
特に平成23年12月に勤務していた会社を
平成24年6月までに退社していた場合は納付書が来ます。
この辺りは少し補足してください。
3.3月31日に退職した時点では
次の会社が決まっていますので、
雇用保険などからは何もありません。
でも、払い損ではなく、
次退職するときに勤務年数に追加されます。
例えば次の会社と残念ながらご縁が無く3ヶ月くらいで退職した場合
次の会社だけでは失業保険をもらう権利は無いですが、
今の会社で7ヶ月以上加入していれば
足し算して1年以上になり失業保険をもらえます。
5年以上や10年以上などで給付日数が変わりますが、
その辺りにも足されますので
払い損ではないので、ご安心を。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
会社を自己都合で辞めた場合と
会社の都合で辞めた場合
失業保険(名前が違っていたらごめんなさい)
でしたっけ
何ヶ月後にもらえて
今までもらっていた給料の半分もらえるとか
流れ見たいのを詳しい方がいましたら教えて下さい
会社の都合で辞めた場合
失業保険(名前が違っていたらごめんなさい)
でしたっけ
何ヶ月後にもらえて
今までもらっていた給料の半分もらえるとか
流れ見たいのを詳しい方がいましたら教えて下さい
昔は失業保険と言いましたが法律が変わり雇用保険といいます。
流れとしては
会社都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒認定日⇒支給期間に入る・・・支給まで約1ヶ月弱
自己都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒給付制限期間3ヶ月支給期間⇒認定日・・・支給まで3ヶ月半~4ヶ月
受給金額は過去6ヶ月の賃金賞与抜きの総支給額)の合計を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%の範囲内が基本手当日額です。給料の安い人は割合が高くなります。
ちなみに試算しますと20万円の人で4605円、25万円で5197円、30万円で5567円、35万円で5833円、40万円で6145円になります。
支給日数は下記のとおり。
自己都合・・・雇用保険保保険者期間(勤務期間ではありません)10年未満で全年齢で90日、10年~20年未満で120日、
20年以上で150日。
会社都合・・・1年未満は全年齢で90日、1年~5年未満で30歳~45歳未満で90日、45歳~60歳未満で180日、
5年~10年未満、30歳未満は120日、30歳~45歳未満で180日、45歳~60歳未満で240日
10年以上20年未満で30歳未満で180日、30歳~35歳で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳未満で270日となっています(後は省略)
結構細かく規定されています。
参考にして下さい。
流れとしては
会社都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒認定日⇒支給期間に入る・・・支給まで約1ヶ月弱
自己都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒給付制限期間3ヶ月支給期間⇒認定日・・・支給まで3ヶ月半~4ヶ月
受給金額は過去6ヶ月の賃金賞与抜きの総支給額)の合計を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%の範囲内が基本手当日額です。給料の安い人は割合が高くなります。
ちなみに試算しますと20万円の人で4605円、25万円で5197円、30万円で5567円、35万円で5833円、40万円で6145円になります。
支給日数は下記のとおり。
自己都合・・・雇用保険保保険者期間(勤務期間ではありません)10年未満で全年齢で90日、10年~20年未満で120日、
20年以上で150日。
会社都合・・・1年未満は全年齢で90日、1年~5年未満で30歳~45歳未満で90日、45歳~60歳未満で180日、
5年~10年未満、30歳未満は120日、30歳~45歳未満で180日、45歳~60歳未満で240日
10年以上20年未満で30歳未満で180日、30歳~35歳で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳未満で270日となっています(後は省略)
結構細かく規定されています。
参考にして下さい。
失業保険について、わからないことが多いので教えてください。
H22.4月~H23.3月まで、私立歯科大学の研修医でした。退職時に、雇用保険被保険者証をもらいました。H23.4月から、町の歯科医
院で働き始め、今月末で退職します。理由は、院長と意見が合わずストレスで体調をくずしたことです。失業保険を受給しようと思いますが、何点かわからないことがあります。
①雇用保険被保険者証は医院から新たにもらえるのですか?
歯科大学退職時に受け取った雇用保険被保険者証は現在も手元にあります。医院入社時に提出するように言われたことはありませんでした。失業保険受給には雇用保険被保険者証の提出が必要ですが、一人につき1枚しか発行されないとのこと。失業保険の申請時には、歯科大学退職時の雇用保険被保険者証を提出することになるのでしょうか?
②退職願を書きましたが、院長から「これを受けとると自己都合退社扱いになるので受け取らない」と言われました。退職は認めるが会社都合ということにしてくれていい、ということらしいです。でも、色々調べてみると、会社都合退社が認められるためには、証拠が必要とあります。残業や休日出勤もかなり多いので、勤務時間は労働基準法に違反するほどのものですが、タイムカード等ないので証拠はひとつもありません。体調をくずしたのも、本当ですがその証拠も特にありません。それでも、院長がいいと言えば会社都合退社ということになるのでしょうか?
③退職とは関係無しに、今年5月に結婚することになっています。失業保険申請中に姓が変わっても受給は可能ですか?勿論、働く意志はあるのですが、結婚のために色々忙しく相手のご両親の介護等もあるので、今すぐにどうしても働かなきゃ!と言うほど焦ってはいません。ゆっくり、合うところを探したいなと思っています。
H22.4月~H23.3月まで、私立歯科大学の研修医でした。退職時に、雇用保険被保険者証をもらいました。H23.4月から、町の歯科医
院で働き始め、今月末で退職します。理由は、院長と意見が合わずストレスで体調をくずしたことです。失業保険を受給しようと思いますが、何点かわからないことがあります。
①雇用保険被保険者証は医院から新たにもらえるのですか?
歯科大学退職時に受け取った雇用保険被保険者証は現在も手元にあります。医院入社時に提出するように言われたことはありませんでした。失業保険受給には雇用保険被保険者証の提出が必要ですが、一人につき1枚しか発行されないとのこと。失業保険の申請時には、歯科大学退職時の雇用保険被保険者証を提出することになるのでしょうか?
②退職願を書きましたが、院長から「これを受けとると自己都合退社扱いになるので受け取らない」と言われました。退職は認めるが会社都合ということにしてくれていい、ということらしいです。でも、色々調べてみると、会社都合退社が認められるためには、証拠が必要とあります。残業や休日出勤もかなり多いので、勤務時間は労働基準法に違反するほどのものですが、タイムカード等ないので証拠はひとつもありません。体調をくずしたのも、本当ですがその証拠も特にありません。それでも、院長がいいと言えば会社都合退社ということになるのでしょうか?
③退職とは関係無しに、今年5月に結婚することになっています。失業保険申請中に姓が変わっても受給は可能ですか?勿論、働く意志はあるのですが、結婚のために色々忙しく相手のご両親の介護等もあるので、今すぐにどうしても働かなきゃ!と言うほど焦ってはいません。ゆっくり、合うところを探したいなと思っています。
③から、回答します。
「雇用保険を受給する場合、大まかに言えば、ハローワークサイドは、「新たな就職先を、毎月探す」条件で、給付する。
手続き済ませる、ハローワークの雇用保険担当課で、「結婚により、名字と自宅が変わる。
その上、結婚後は相手のご両親を介護する事になる為、就職先探しが暫く出来なくなる。
給付可能か等、雇用保険的にはどうなるか?」を、担当の職員さんに相談した方が良い」です。
①は…
「この手のケースは、「必要な時に、紛失してる」人が、多い。
院長先生又は、総務(社会保険)担当の職員さんに、「歯科医院がある、地域を受け持つ」ハローワークへ、再発行として取り寄せにより、手配して貰った方が良い」です。
②は…
「歯科医院から、「会社都合で、退職した」旨の証明書が、発行されたなら、手続きさえ済ませれば、比較的スグ(早い人だと、手続き済ませた日の翌月)に給付される。
しかし、中々発行して貰えないなら、ハローワークの雇用保険担当課で、一度相談した方が良い。
労働基準法違反の部分は、「勤務時間分かる、メモ書きでも、法的な証拠として、認められた」ケースある。
「分かる範囲内で、思い出して書いた」メモ書き持って、「歯科医院ある地域又は、住んでる地域、何れを受け持つ」労働基準監督署で、一度相談した方が良い。
ただ、労働基準法関係で手続き済ませる場合、法的な面から一度弁護士さんか司法書士さんで、法律相談した方が良い
(どちらの相談も、日時か場所に条件付く場合あるが、無料法律相談可能な場合有り)」です。
①~③共に、特記無ければ、回答の中の「ハローワーク」は、全て…
「住んでる地域を、受け持つハローワーク」と、します。
「雇用保険を受給する場合、大まかに言えば、ハローワークサイドは、「新たな就職先を、毎月探す」条件で、給付する。
手続き済ませる、ハローワークの雇用保険担当課で、「結婚により、名字と自宅が変わる。
その上、結婚後は相手のご両親を介護する事になる為、就職先探しが暫く出来なくなる。
給付可能か等、雇用保険的にはどうなるか?」を、担当の職員さんに相談した方が良い」です。
①は…
「この手のケースは、「必要な時に、紛失してる」人が、多い。
院長先生又は、総務(社会保険)担当の職員さんに、「歯科医院がある、地域を受け持つ」ハローワークへ、再発行として取り寄せにより、手配して貰った方が良い」です。
②は…
「歯科医院から、「会社都合で、退職した」旨の証明書が、発行されたなら、手続きさえ済ませれば、比較的スグ(早い人だと、手続き済ませた日の翌月)に給付される。
しかし、中々発行して貰えないなら、ハローワークの雇用保険担当課で、一度相談した方が良い。
労働基準法違反の部分は、「勤務時間分かる、メモ書きでも、法的な証拠として、認められた」ケースある。
「分かる範囲内で、思い出して書いた」メモ書き持って、「歯科医院ある地域又は、住んでる地域、何れを受け持つ」労働基準監督署で、一度相談した方が良い。
ただ、労働基準法関係で手続き済ませる場合、法的な面から一度弁護士さんか司法書士さんで、法律相談した方が良い
(どちらの相談も、日時か場所に条件付く場合あるが、無料法律相談可能な場合有り)」です。
①~③共に、特記無ければ、回答の中の「ハローワーク」は、全て…
「住んでる地域を、受け持つハローワーク」と、します。
失業保険の需給期間について教えてください。よろしくお願いします。
私は会社を病気のため退職し、失業保険の受給期間を延期してもらい、現在治療しています。働ける状態になって失業保険の需給申請した場合、どのくらいもらえるものなのでしょうか?いろいろ人に聞いてみたり、インターネットで調べてみましたが、いまいちわかりません。
ちなみに、
2005年4月1日入社、2010年3月31退職
退職理由は、一身上の都合としましたが病気とも記載してもらっています
退職時、42歳でした。
病気等の場合、特定需給資格に相当すると聞きましたが、その場合、5年未満・以上でかなり需給額が変わると聞きました。
無職の上、大変お粗末な話ですが、お詳しい方宜しくお願いします。
私は会社を病気のため退職し、失業保険の受給期間を延期してもらい、現在治療しています。働ける状態になって失業保険の需給申請した場合、どのくらいもらえるものなのでしょうか?いろいろ人に聞いてみたり、インターネットで調べてみましたが、いまいちわかりません。
ちなみに、
2005年4月1日入社、2010年3月31退職
退職理由は、一身上の都合としましたが病気とも記載してもらっています
退職時、42歳でした。
病気等の場合、特定需給資格に相当すると聞きましたが、その場合、5年未満・以上でかなり需給額が変わると聞きました。
無職の上、大変お粗末な話ですが、お詳しい方宜しくお願いします。
基本手当の所定給付日数は、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合、「退職時の年齢が42歳」「被保険者であった期間5年以上10年未満」では180日となります。
よって、「被保険者であった期間1年以上5年未満」では90日ですので、被保険者であった期間が5年未満と5年以上では90日の違いがあります。
ただし、これには補足があり、
『特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。』
とあります。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合は、この「特定理由離職者の範囲」の2.に該当します。
つまり、質問者さんは、補足の『離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日』の期間には該当しますが、ただし書き以降の『「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り』には該当しませんので、被保険者であった期間が5年以上であろうとなかろうと、基本手当の所定給付日数は一般離職者と同様の「90」日となります。
よって、「被保険者であった期間1年以上5年未満」では90日ですので、被保険者であった期間が5年未満と5年以上では90日の違いがあります。
ただし、これには補足があり、
『特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。』
とあります。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合は、この「特定理由離職者の範囲」の2.に該当します。
つまり、質問者さんは、補足の『離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日』の期間には該当しますが、ただし書き以降の『「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り』には該当しませんので、被保険者であった期間が5年以上であろうとなかろうと、基本手当の所定給付日数は一般離職者と同様の「90」日となります。
大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
結論;昼間が学生で、労働が夜間ですから、加入は不可になります。
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
関連する情報